Your eyes only.
それは、はじめての感情だった。
心配そうな瞳の、小さな少年。
幼い少年の、褐色のまなざしが、闇に沈む僕の心をあたためる唯一の、ものだった。
横一線に、ナイフをひらめかせる。
声もなく、ただ驚いたように見開かれた双のひとみが、てらりと月光を弾いた。
すぐに、それも、消えてなくなる。
僕は、それを地面に残し、闇に消えた。
やがて、遠いパトカーのサイレンに、口角が持ち上がってゆく。
ボスが、モナリザ・スマイルだな――と、つぶやく、いつの間にか習いになってしまった、意味のない笑いだった。
星のない夜空に、細い月がぼんやりと霞む。
シャトー・マルゴーの深いブーケが、鼻先をかすめた。
灯を消したままの部屋の出窓に腰かけて、僕はワインを一口啜った。
やがて、遠く離れた向かいの窓に、ひとりの少年が現れる。
あの窓に彼が越してきたのは、奇跡に近い偶然だった。
僕は、ひと目見て、気づいた。
少年は、僕には気づいていない。
覚えてすらいないのに違いない。
八年も昔の、ただ一度の出来事など。
それでも―――
一番辛かった時の、あたたかな思い出は、僕の心の奥底に、しずかに、まどろみつづけている。やわらかな、記憶となって。
今夜も、彼の姿を見ることができた。
ふわふわと、決してワインのせいばかりではない酔いに身をまかせて、僕は、静かに、瞼を閉じる。
それが、僕の、就眠儀式だった。
それは、なんと偶然だったのだろう。
同じ町に暮らしながら出会うことすら、皆無であったのに。
旅先(・・)のホテルで、僕は、彼を見つけ出した。
森と湖の、心地好い空気の中で、彼は、笑っている。
明るい笑顔は、惜しみなく連れに、投げかけられていて、僕は、少し、胸が苦しかった。
ふっと、逸れた視線が、僕を捉えた――ように、見えた。
やはり、明るい笑顔のまま、彼は、
「すみません」
と、僕に、声をかけてきた。
僕は、不様に狼狽えなかっただろうか。
「なにか?」
声が、震えはしなかったか。
「撮ってもらえますか」
「かまいませんよ」
上手く笑えただろうか。
手渡されたカメラのレンズ越しに、僕は、君を、思うさま、眺めやる。おかしくは思われないていどの時間を、心がけて。
フラッシュが光る。
「はいどうぞ」
「ありがとう」
後頭部を掻きながら、少年が、カメラを受け取った。
「よい旅行を」
「君も」
手を振り返して、僕は、踵を返した。
仕事が首尾よくゆけば、また、窓の中の君に会うことができるでしょう。
彼を見ている僕だから、それに気づいたのだろう。
僕以外の、視線に。
それが、危険なものだということに気付いたのは、僕の職業のせいだろうか。
けれど、彼は気付かない。
グループの中で、明るく自然体だ。
仲間の中の視線に、気づく気配すらなかった。
だから、僕は、気をつけていた。
僕のほうの仕事は、どうせ、すぐに片がつく。
呑気に笑っている、赤ら顔の男。彼が、今回の僕のターゲットだった。
男の滞在期間は二週間。
彼の滞在期間は、十日。あと、七日残っている。
大丈夫。
焦る必要は、ない。
彼が無事帰った後に、仕事にかかることを、僕は決めた。
せめて、彼が血なまぐさい思い出を作らずにすむように。
そんな僕の願いは、しかし、聞き届けられることはなかった。
時刻は、深夜、零時四十五分。
月明かりに照らされて、ほんのりとやわらかな霧が、周囲を閉ざす。
僕の視線の先には、黒い影。
細い小道の先は、確か、崖になっていたはずだ。
こんな深夜に、彼はどこへ向かうのだろう。
彼の生活を知っていれば、彼がこんなに夜遅くまで起きていることなど稀だと、わかるだろう。
木々の隙間を縫うように、彼は、歩いている。
ふと、逢瀬――などということばがひらめいたのは、彼の後に続く影に気づいたからだ。
そうだったら、引き返すべきでしょうか。
野暮だったか――と、僕が踵を返そうかと惑った時だった。
「うわっ」
という悲鳴が聞こえた。
声の主など、わざわざ考えるまでもなかった。
霧のスクリーン越しに、彼が、誰かに首を絞められているシーンが映し出されていた。
手が、自然に、愛用のナイフを握りしめていた。
彼に見られるかもしれない。
危惧は、彼の腕が、救いを求めるかのように伸ばされたことで、霧散した。
霧の中。
僕は、気配を消して、彼を殺そうとしている誰かの背後に回りこむ。
そうして。
もはや、迷いはなかった。
僕は、ナイフを、横に引いた。
はじめてひとを殺した瞬間に、僕の心は、凍りついた。
あれから、幾人をこの手にかけてきただろう。
ターゲットに返り討ちにされたあの日。
何も感じないはずの僕の心は、忸怩とした悔しさに囚われていた。しくじったという、屈辱――ただそれだけが、僕をかろうじて生かしていたのかもしれない。
気がついたとき、僕の目の前には、明るい茶色の瞳があった。
丸い頬。長めの褐色がかった髪の毛を後ろでひとつに括っている、十になるかならないかといったくらいの少年だった。
金田一はじめ――――あれから一時として忘れたことのない名前の少年は、僕を見て、笑った。
生きていてよかった――と、そう言って、笑ったのだ。
あれから数日を、僕は、彼に看病されて過ごした。
動けるようになるまでのほんの数日間が、僕の心の底に眠る、宝物だ。
あの、褐色のまなざしが、僕の、ただひとつ。
たとえ、彼と交わることがありえないにせよ、彼がこの世界のどこかに生きていてくれること、それが、僕の、たった一つの望みだった。
血に汚れたこの僕が、ただひとりの無事を願う。
その、このうえない皮肉。
しかし――――――
霧に閉ざされた視界の先、見ることができるのは、彼の輪郭のみだった。
それでも、僕は、彼の顔を思い描くことができる。
寸毫もたがえることなく。
探る掌の下に、彼の脈動を感じる。
生きている。
よかった。
意識のない彼の上半身を、僕は、きつく抱きしめ、そっとくちづけた。
はぁ………
押し出すように息をつく。
僕としたことが。
生涯二度目のしくじりは、間違いなく、僕の命を奪ってゆこうとしている。
ターゲットは、凡庸な男であったのに。
クッ……。
思わずこぼれた笑いのせいで、咳がこみあげてきた。
ポタリ。
雨音のような音をたてて、あふれ出した血が、部屋の床を濡らしてゆく。
はじめくん。君は今頃なにをしているのでしょうね。
出窓の向こう、いくつもの鮮やかな光に混じって、あたたかそうな光のあふれる窓が、ぼんやりと見える。
眠っている?
眠っているのなら、君の眠りが、安からんことを。
いつも。
君が安らかな眠りを楽しめることを、僕は祈っていますよ。
出窓の桟についた手の感触は、もう、ない。
僕は、ゆっくりと、瞼を閉じる。
彼の瞳と同じように、あたたかな光あふれる窓が、いつまでも、僕を見ているかのようだった。
おわり
start 11:12 2005/12/20
up 14:10 2005/12/20
あとがき
久しぶりの高金オンリー話なのに、よりによって死にネタって。
いつもお世話になっているので、Tさま宅へ差し上げさせていた
だこうかなと思ってたのですが……内容があんまりかなと思わない
こともないのでパスにすることに。
最初は、もう少し、救いのある話になる予定だったのですよ。
それが~~~~。一方通行の独白。しかも、高遠くん、死んでし
まうし………。これって、どうよ? って感じですよね。
魚里はこういう方向性が勝ってるんだということで、お目こぼし
くださいませ。
少しでも、楽しんで(?)いただけるといいのですが。
_____________________________
「パスしようかと…」と、魚里さまが仰っていたのにも拘らず、
いただいてしまいましたvv
ふっふっふっふっふっ。いつもより、「ふっ」増量中です!
竹流は、何気に死にネタも大好きですよ~vv
一方通行っていうのも、純愛で、また良しvですよねvvv
ええ、ある意味、かなり萌えです///
思わず拙い挿絵を描いてしまいました////
魚里さま、素敵なお話を、ありがとうございましたvv!
大事にいたしますね!!!
この素敵なお話を書かれた、魚里さまのサイトはこちらから。
↓
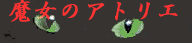
素敵小説が、たくさん楽しめますv
05/12/27UP
再UP14/08/25